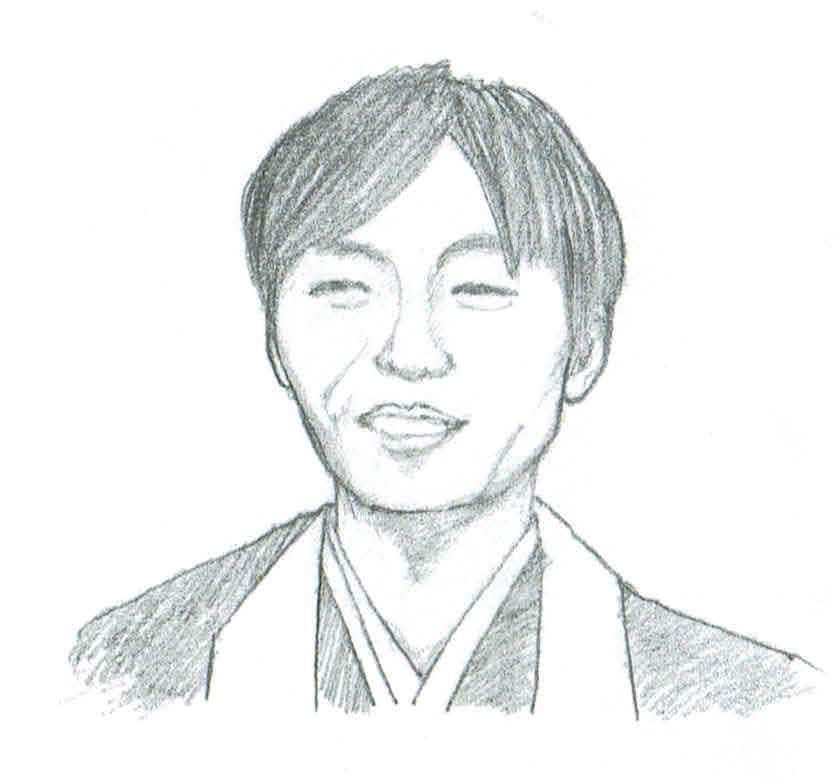
ロバートさんを除くと、内平さん以降のお三方は曹洞宗以外のお坊さんだ。
内平さんは浄土真宗のお坊さん。ご自身のことを深く対象化されていて、一つ一つの言葉が粒立って届いてくる。僧侶になることで変化したご自身の有り様のお話など、とても興味深い。
「信じる心も頂く、と考えるんです。同じように、自分で唱えているんだけど、それは自分が唱えているんじゃなくて、唱えながらもお声を聞かせてもらってるんだよ、って考えるんですよね。」
「教えというか、何かそういうものが体の中にあるのであれば、お坊さんかどうかは関係ないというか…。でもお坊さんであることで物事の見え方は多少違うんじゃないかって。」
もともと純文学を学んでいた内平さんは、その後京都で僧侶になるための勉強を経てご実家のお寺に戻る。実際に、個々に現実的な悩みを抱えた檀家さんたちとコミュニケーションをとると、そこには”ギャップ”があった。
「学んで帰ってきてすぐのときは”教えはこうなんだ”って、頭が完全に出来上がっています。でも帰ってきたら、やっぱりぶつかっちゃうんですよね。みなさんが相談して下さるのは”亡くなった主人が、私の枕もとに立つんです。何を伝えようとしているのでしょうか?”とか、教えとは少し離れた部分というか…。思ってもみないことを聞かれるんです。霊の存在の有無に関しては、お釈迦様は在るとも無いともおっしゃっていません。学んでないことを尋ねられます。そして、そもそも、僕たちが伝えたいことと皆さんが知りたいことは、最初からはリンクしないものです。」
「僕も好きで美術館に作品を見に行くんですけど、解説が邪魔だと思うことがあります。解説じゃなくて、作品と僕との対話があって、対話に意味があるんじゃないかなって思うんです。お寺も“はい、教えはこうです”ではなく、対話があって、そこに矛盾がありながらも、対話こそが宗教の場なんじゃないかと思うんです」
「10代の頃から澁澤龍彦や中井英夫が好きで、あれこそ関係性から生まれてきた芸術だと思うんですよね。憧れがありますね。多分単体では生まれなかったと思うんですよ。」
僧侶としての経験と認識の深まりが、内平さん自身の内面に影響を与えていく。
「“私”って、関係性の中にあると思うんですよね。若いころは自分が自分がって考えてたんですけど。もっと場でありたいというか。私っていうのが、関係性のつなぎ目のひとつでいいのかなって思うんですよね」
「流れに身を任せるのがいいのかなって。その上で自分があるのがいいのかなって。そこはお坊さんになって変わったところですね。昔は自分が大切だったんです。以前は自分の時間が大切で、他人に興味が無かったんです。お坊さんになってみて他人のために時間を使うとか、人に何かあげるとか、そういうことの重要性が増してますね」
訥々と語る言葉からは、私たちの生活感覚や思いと地続きに内平さんがお坊さんとして存在してくれているように感じられてくる。
「親鸞聖人も自分の愚かさを下りて行ったところに、明るさがあった…強さを目指していくのではなく、弱さを掘り下げていったところに開かれたところがあるというか…。僕自身はあまり感情の起伏が無いのですが、自分の愚かさを見せるっていう方は多いみたいですね。同じような目線で、同じように悩む。」
「北海道の歴史性の無さっていうのは絶対的なものですよね。ウチも古い方ですけど、それでも120年ぐらいのものなので。本州って下手したら1000年とか…その歴史性の無さっていうのが自由さを生んでいると思うんですよね。建物一つでもそうですし、地縁血縁じゃない部分を当初から作ってきたと思うんです。お寺も自分で選択して、そこからコミュニティが生まれてきた。歴史性の無さが利点になっていると思いますね」
「語り継がれているっていうことは、その存在がまだあるってことだと思うんですよ。語り継いでその関係性を大切にしていくことが僧侶の仕事かなって思うんです」